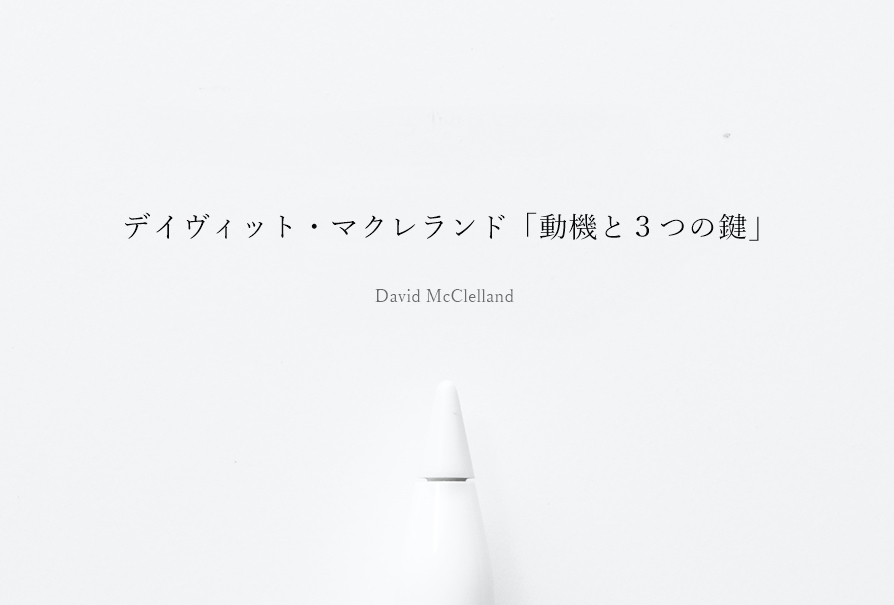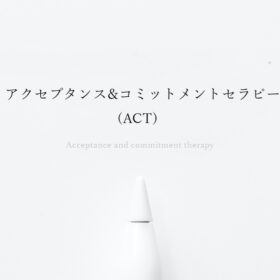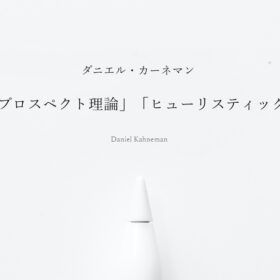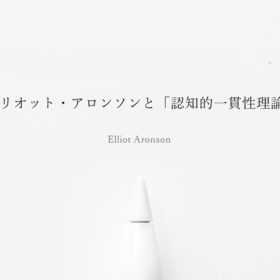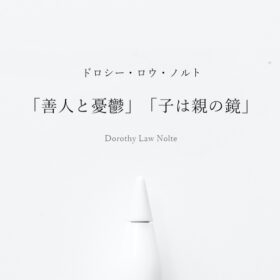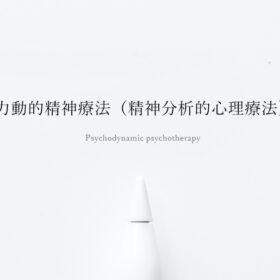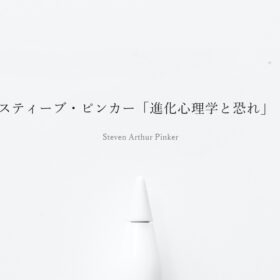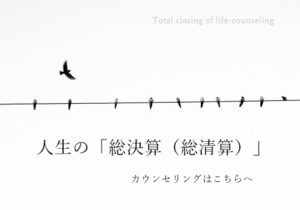心理学者・臨床家・研究者の人物像や提唱された内容から今に学べることは多くあります。
ここではデイヴィット・マクレランド「動機と3つの鍵」について書いていきたいと思います。
デイヴィット・マクレランドについて
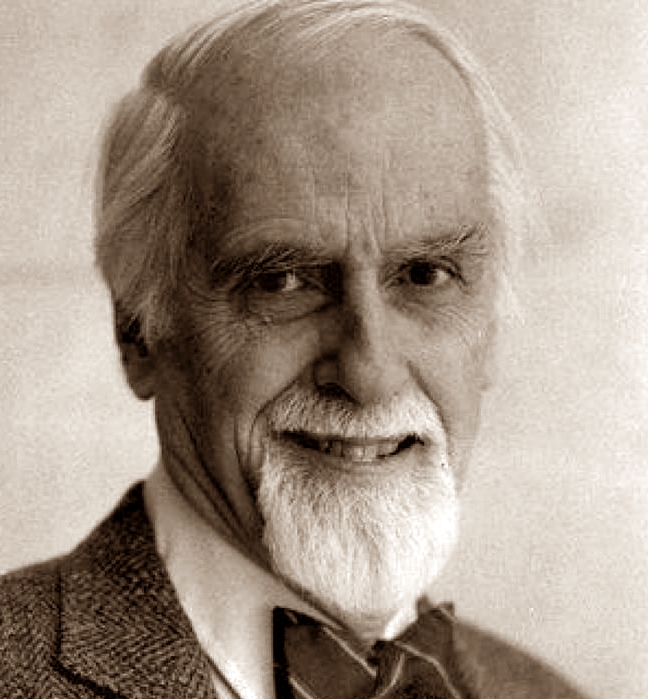
デイヴィット・マクレランド(David McClelland)は1917年ニューヨーク州マウント・ヴァーノンに生まれました。
ウェズリーアン大学で学士号を取得し、ミズーリ大学で修士号を、イエール大学で実験心理学の博士号を取得します。
コネチカット大学とウェスレアン大学で教職に就いた後、1956年ハーバード大学で約30年間教壇に立ち、心理学と社会関係学科の会長を務めました。
1963年には経営マネジメント・コンサルタントを立ち上げ、その理論をスタッフ評価と研修に携わる会社幹部支援のために応用します。
1987年にはボストン大学へ移り、アメリカ心理学賞を受賞しました。
主著には、
1953年「達成動機」
1961年「達成する社会」
1973年「知能ではなく能力をテストすること」
1987年「モチベーション:達成・パワー・親和・回避動機の理論と実際」
1998年「能力と行動上の出来事との同一化ーインタビュー」
などがあります。
動機と3つの鍵
1960年代から1970年代のアメリカの雇用採用は学歴と性格テスト、IQテストによって決められていました。
そんな中、マクレランドは「人の動機こそが仕事場で成功するかしないかを決める最良な予言である」と考えました。
その動機は、
①力への欲求(他者への影響をもたらし、管理しようとする衝動)
②達成への欲求(努力を惜しまず、うまく改善しようとする衝動)
③帰属への欲求(他者との間にあたたかい人間関係を形成・維持しようとする衝動)
の3つの欲求の内、一つが主導的なものになり、当人の作業効率を形づくるとマクレランドは主張しました。
支配したいという「力への欲求」はマネージャーやリーダーにとって重要な動機ではあるものの組織と会社のために発揮されなければチームとして機能しなくなります。
マクレランドの考えでは、質の高い仕事は「達成への欲求」から生まれると考えました。
目標に向かって向上し、競争心を駆り立てるからです。
「帰属への欲求」は他者との良好な関係を好みますので、その傾向が強いものはマネージャーになることはまずないと言います。
これらの動機付けは、無意識のうちに埋め込まれた人格的特性に由来するとしています。
それは自覚的に気づいている人は少なく、ヘンリー・マレーとクリスチアナ・モーガンらが考案した無意識の諸相を表に出す「主題統覚検査(TAT)」を活用することをお勧めしている。
■主題統覚検査(TAT)
TATはロールシャッハ・テストに代表される被験者の無意識的なパーソナリティ(性格傾向)を測定することを目的とした投影法の検査の一つです。TATでは人物やあらゆる状況が描かれたカードを提示し、被検者に自由なストーリーを語ってもらい、それを臨床家が分析する方法を取っています。
マクレランドは、このTATの結果をリクルートの側面で分析する革新的な仕組みを考案し、ビジネスにおける採用面で大きな貢献をしています。
参考文献
心理学大図鑑 キャサリン・コーリンほか

記事監修
公認心理師 白石
「皆様のお役に立つ情報を提供していきたいと思っています」
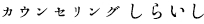
全国どこからでも専門的なカウンセリングと心理療法を受けることができます。
電話番号:090-2862-4052
メール:mail@s-counseling.com