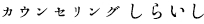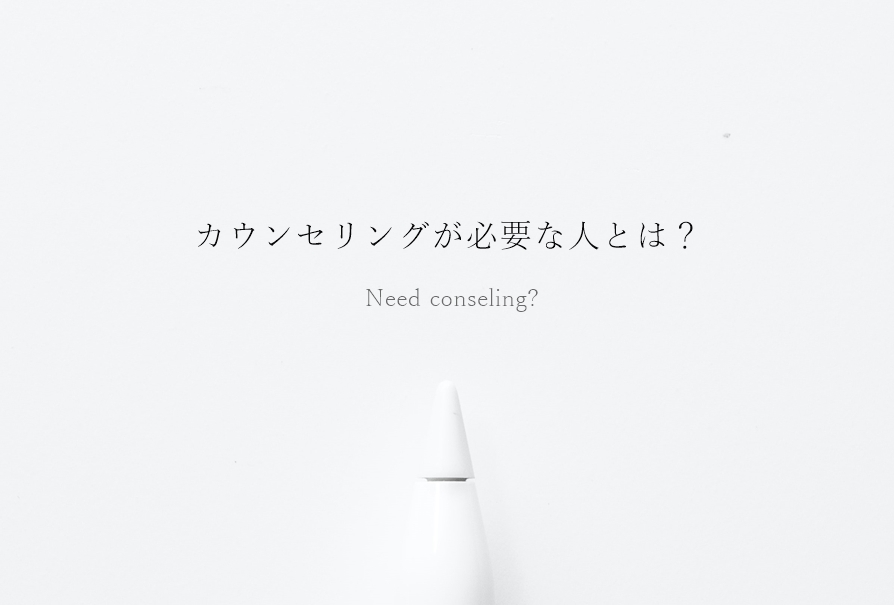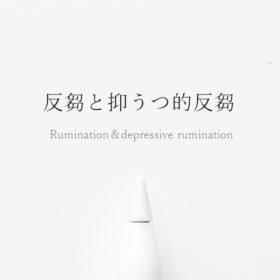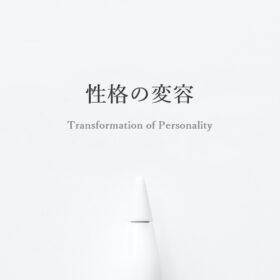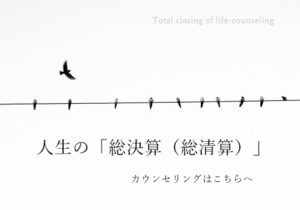「カウンセリングを受けたほうがいいのか?」
「まだ受ける段階ではないのか?」
「実際どのような人が受けているのかわからない」
「受けたら依存してしまうんじゃないか?」
「やっぱり自分で乗り越えなきゃいけないんじゃないか?」
などカウンセリングを受けるべきか否か、どれくらいの状態になったら受けるべきか、などなかなかわからなかったり、迷ったりしてしまうことがあります。
少しでもその点の曇りが晴れますように説明と考察をしていきたいと思います。
もくじ
「カウンセリングが必要な人」という目安が知りたい
カウンセリングが必要な人はどのような人なのか?気になることがあります。
カウンセリングに興味があるけど、一体どのような人が受けていて、どのようなタイミングで受ければいいのか?なかなか判断が難しいものです。
自分の限界を感じてカウンセリングを受けられる方もいれば、なんとなく興味が沸いて受けられる方もいます。
なかなか目安を設定をすることが難しいものですが、「自分が興味を持ってカウンセリングを行いたいとき」がカウンセリングを行うタイミングとしてちょうど良いと思います。
しかし「カウンセリングが必要な人」という場合、カウンセリングを行ったほうが良い人、カウンセリングを行う必要性がある人という意味ですのでこれでは答えになっていません。
本人が興味がなくても、やりたくなくてもカウンセリングが必要かというと人によりけりです。
興味がなくてもやっていると興味が湧き、やりたい気持ちが出てきてうまくいくケースもあれば、やりたくない意思が変わらず、まったくカウンセリングが進まないこともあります。
カウンセリングをやる意思のない方に対してカウンセリングを行うことは難しいことが多く、周囲の方がその方を理解し、サポートするためのカウンセリングや心理教育を行う方が多いかもしれません。
周囲が変化してくると自分もやってみたいと当人が変化してくることもあります。
一般的な表現である「病んでいる」という状態=カウンセリングが必要というわけではないということです。
重篤な場合の第一選択は病院やクリニックなどの医師の診察を受けるべきで、併用してカウンセリングを行うことは有効なこともあります。
さて「カウンセリングが必要な人」という意味が自分なのか?家族や友人など他人のことなのか?によって意味も変わります。
他人の場合、「カウンセリング受けたら?」と言うと良い場合もあれば、「自分はそんなに落ちていない!!」と怒りや否認の思いを強めてしまうこともあり、慎重に考えなければなりません。
自分の場合、「自分はカウンセリングが必要なところまで落ちたのかな?」と受け入れ難さを感じてしまう方もいます。
どちらにしてもカウンセリングを受けるのはそんなに悪しきことなのか?
そんなにカウンセリングを受ける自分はだめなのか?
を改めて見直す必要があります。
なにかダメなことやダメな状態という認識が強すぎる傾向があるかもしれません。
確かにそのようなことはないに越したことはないのですが、人生を生きていると「どん底を味わったり」「苦難」はあるものです。
人生で起きる大きな出来事をライフイベントというのですが、そのようなライフイベントで大きな衝撃やストレスを受けてそのような状態になることがあります。
誰でもなることがあるのです。
そのような視点がなく、なんで自分はこうなんだろう?とかなんであの人はいつもこうなんだろう?という側面だけを感じているとこのような視点が抜け落ちてしまいます。
人によって起こるライフイベントも異なり、重なってしまう人もあれば、運良くあまりストレスに感じることが少ない方もいます。
夏目誠、村田弘によって発表されたライフイベントに対するストレス度を数値化するスケールを2つ紹介します。
これはライフイベントのストレスを数値化したもので、ある程度の目安として参考になります。
①「勤労者のストレス点数のランキング」
大企業に就業中の勤労者1603名(女性308名)による調査です。
| ストレッサー | 全平均 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 配偶者の死 | 83 | 83 | 82 |
| 会社の倒産 | 74 | 74 | 74 |
| 親族の死 | 73 | 71 | 78 |
| 離婚 | 72 | 72 | 72 |
| 夫婦の別居 | 67 | 67 | 69 |
| 会社を変わる | 64 | 64 | 62 |
| 自分の病気やケガ | 62 | 61 | 67 |
| 多忙による心身の疲労 | 62 | 61 | 67 |
| 300万円以上の借金 | 61 | 60 | 65 |
| 仕事上のミス | 61 | 60 | 65 |
| 独立・起業 | 61 | 61 | 61 |
| 単身赴任 | 60 | 60 | 60 |
| 左遷 | 60 | 60 | 59 |
| 家族の健康や行動の大きな変化 | 59 | 48 | 63 |
| 会社の立て直し(リストラ) | 59 | 59 | 58 |
| 友人の死 | 59 | 58 | 63 |
| 会社が吸収合併される | 59 | 59 | 58 |
| 収入の減少 | 58 | 58 | 57 |
| 人事異動 | 58 | 58 | 58 |
| 労働条件の大きな変化 | 55 | 54 | 56 |
| 配置転換 | 54 | 54 | 55 |
| 同僚との人間関係 | 53 | 52 | 57 |
| 法律的トラブル | 52 | 52 | 51 |
| 300万円以下の借金 | 51 | 51 | 55 |
| 上司とのトラブル | 51 | 51 | 50 |
| 抜てきに伴う配置転換 | 51 | 51 | 52 |
| 息子や娘が家を離れる | 50 | 50 | 50 |
| 結婚 | 50 | 50 | 50 |
| 性的問題・障害 | 49 | 48 | 50 |
| 夫婦げんか | 48 | 47 | 52 |
| 家族が増える | 47 | 46 | 52 |
| 睡眠習慣の大きな変化 | 47 | 47 | 50 |
| 同僚とのトラブル | 47 | 45 | 54 |
| 引っ越し | 47 | 46 | 50 |
| 住宅ローン | 47 | 46 | 50 |
| 子供の受験勉強 | 46 | 44 | 53 |
| 妊娠 | 44 | 43 | 50 |
| 顧客との人間関係 | 44 | 44 | 47 |
| 仕事のペース・活動の減少 | 44 | 45 | 43 |
| 定年退職 | 44 | 44 | 42 |
| 部下とのトラブル | 43 | 43 | 45 |
| 仕事に打ち込む | 43 | 43 | 44 |
| 住宅環境の大きな変化 | 42 | 42 | 45 |
| 職場の人数が減る | 42 | 42 | 43 |
| 社会活動の大きな変化 | 42 | 41 | 43 |
| 職場のOA化 | 42 | 41 | 45 |
| 家族メンバーの大きな変化 | 41 | 40 | 44 |
| 子供が新しい学校へ変わる | 41 | 40 | 45 |
| 軽度の法律違反 | 41 | 40 | 43 |
| 同僚の昇進・昇格 | 40 | 41 | 37 |
| 技術革新の進歩 | 40 | 40 | 41 |
| 仕事のペース、活動の増加 | 40 | 41 | 39 |
| 自分の昇進・昇格 | 40 | 40 | 41 |
| 妻(夫)が仕事を辞める | 40 | 35 | 61 |
| 職場関係者に仕事の予算がつかない | 38 | 38 | 38 |
| 自己の習慣の変化 | 38 | 37 | 42 |
| 個人的成功 | 38 | 37 | 40 |
| 妻(夫)が仕事をはじめる | 38 | 38 | 37 |
| 食習慣の大きな変化 | 37 | 36 | 42 |
| レクリエーションの減少 | 37 | 37 | 36 |
| 職場関係者に仕事の予算がつく | 35 | 35 | 33 |
| 長期休暇 | 35 | 34 | 37 |
| 職場の人数が増える | 32 | 32 | 32 |
| レクリエーションの増加 | 28 | 27 | 30 |
| 収入の増加 | 25 | 25 | 23 |
②主婦のストレス点数のランキング
424名の主婦を対象とした調査からストレス点数を高い順にランキングしたものです。
| ストレッサー | ストレス度 |
|---|---|
| 配偶者の死 | 83 |
| 離婚 | 75 |
| 夫の会社の倒産 | 74 |
| 子どもの家庭内暴力 | 73 |
| 夫が浮気する | 71 |
| 夫婦の別居 | 70 |
| 自分の病気やケガ | 69 |
| 親族の死 | 69 |
| 嫁・姑の葛藤 | 67 |
| 夫がギャンブルをする | 66 |
| 家族の健康や行動の大きな変化 | 64 |
| 友人の死 | 63 |
| 多忙による心身の疲労 | 63 |
| 法律的トラブル | 61 |
| 近所とのトラブル | 61 |
| 上司とのトラブル | 60 |
| 300 万以上の借金 | 60 |
| 収入の減少 | 59 |
| 親族とのトラブル | 59 |
| 夫の単身赴任 | 58 |
| 親との同居 | 57 |
| 労働条件の大きな変化 | 56 |
| 転職 | 56 |
| 話し相手がいなくなる | 56 |
| 睡眠パターンの大きな変化 | 55 |
| 家族パターンの大きな変化 | 55 |
| 夫婦げんか | 55 |
| 夫の定年退職 | 55 |
| 住宅環境の変化 | 55 |
| 引越し | 54 |
| 仕事を辞める | 54 |
| 子どもの受験勉強 | 53 |
| 妊娠 | 53 |
| 息子や娘が家を離れる | 53 |
| PTA や自治会の役員になる | 53 |
| 性的問題・障害 | 52 |
| 軽度の法律違反 | 51 |
| 夫の転勤・配置転換 | 51 |
| 300 万円以下の借金 | 51 |
| 乳幼児の養育 | 51 |
| 結婚 | 50 |
| 子どもの成績が下がる | 50 |
| 住宅ローン | 49 |
| 子どもが新しい学校へ変わる | 49 |
| 教師・保母との人間関係の変化 | 49 |
| 家族との会話の減少 | 48 |
| 食生活における大きな変化 | 45 |
| 体重の増加 | 45 |
| 自己の習慣を変える | 43 |
| レクリエーションの減少 | 42 |
| 個人的な成功 | 38 |
| 自分の昇進・昇格 | 37 |
| 体重の減少 | 36 |
| 長期休暇 | 34 |
| 技術革新の進歩 | 34 |
| 夫の昇進・昇格 | 33 |
| 近所の人との和解 | 32 |
| 夫婦の和解 | 31 |
| レクリエーションの増加 | 31 |
| 子どもが志望校に合格 | 30 |
| 話し相手が増える | 30 |
| 家族との会話の増加 | 29 |
| 収入の増加 | 28 |
| 子どもの成績が上がる | 28 |
実際どのような人がカウンセリングを利用している?
実際どのような人がカウンセリングを利用しているのでしょうか?
相談される窓口によって異なりますが、意思疎通ができる子供から高齢者まで幅広く利用されています。
多く相談されるものとして
・抑うつやうつ病
・人間関係の問題
・仕事の悩みやストレス
・恋愛や結婚にまつわる問題
・精神疾患
・体に関する悩み
・ストレスの蓄積
・精神的ショックな出来事
・家族の問題
・性格的特徴の悩み
・子育てと疲労
・不安や恐怖
・ストレス症状
・生きがいや生き方
などがあります。
また問題や悩みがなくても「より高めたい」「より良くしたい」ということからカウンセリングを用いて自分を成長させるために活用される方もいます。
カウンセリングを利用される方を大別すると
「悩みや問題を改善、軽減、解決をするために利用する方」
「自分の成長を目的として利用する方」
「こころのメンテナンスや良い状態を維持するために活用する方」
がいらっしゃいます。
近年カウンセリングが少しずつ身近なものになってきましたが、欧米での活用と比較するとまだまだ浸透していないのが日本の現状です。
「うつになったら受けるもの」というイメージや「カウンセリングを受ける=良くない・ダメな人」といったイメージがいまだにあったりするかもしれません。
確かにそのように思う人も今でもいるかもしれませんが、実際はさまざまな人が利用されています。
会社の役員や社長、有名人など著名な方で普段誰かに相談することが難しい立場の方もいれば、自分自身の為にポジティブに活用される方もいます。
利用したほうが時間的にも結果的にも「有益」という判断で専門家に相談する方もいるのです。
知っておられる方はご存知かもしれませんが、プロのアスリートやアクティブに活動している一般の方でも自分専属のカウンセラーやコーチをつけて「より良い状態」を維持・向上に努めています。
もちろん、こころの悩みや問題を抱えている人や自分だけでは乗り越えられない難しい問題を抱えている人の相談も多くあります。
少しずつ利用する意図が時代によって拡大してきているように感じます。
日本では伝統的に「自分のことは自分で」という自立心を育てていくことを大切にしてきましたが、それが過剰になっていることも問題になっているかもしれません。
それは「相談できない」「弱みを見せられない」といった問題が該当すると思います。
ストレス・コーピング(ストレス対処能力)が高い人ほど、人に相談できる能力が高いとされていることをご存知でしょうか?
これは日本の伝統的な教育とある意味反してしまいます。
ある程度の自立心を持ちながら、何かあれば人や専門家に相談するほうが効率がよく、安全性も担保され、ともに協力して生きていける人生を歩むことができます。
バランスがとても大切だということです。(そのバランスは人によって異なります)
昔の日本は「切腹」という文化を持っていたほど自分に厳しく律することを重んじました。
過去では素晴らしい文化であったかもしれませんが、現代では過度な自責や自害に繋がりかねません。
弱さを受け入れ、弱さを見せられるほどストレスは少なくなり、生きやすくなるものです。
欧米では、カウンセリングは自己管理の一種としても用いられ、自分のメンタルを整える場所という位置づけで利用されている方も多くいます。
日本でもそのような利用のされ方が少しずつ増えてきています。
カウンセリングの内容のイメージとして「話を聞いてもらうところ」というイメージがありますが、実はそのイメージは実際の半分以下の説明でしかありません。
制約があまりない、秘匿性のある安全な場で受容的・共感的に話を傾聴される経験をしたことがない方には、その魅力と素晴らしさは理解できないかもしれません。
なかなか現実的にそのような経験は体験できません。
しかも実生活と関係のない第三者であるカウンセラーに相談するため、本音で話すことが行い易くなります。
カウンセリングの大事なポイントとして「主体性」があります。
話をしていきながら、自らが気づき、理解し、改善や修正をしていく「主体性」が実は非常に大切であったりします。
カウンセラーがなんでもアドバイスをしたり、言い当てたりするばかりではありません。
この主体性があるから欧米的な自己管理として、話をしながら自らを知り、自分で改善策を考えていくことができます。
またカウンセリングを受けるとそのような主体性を育てることになり、客観視できる「メタ認知能力」や対処できる「コーピング能力」を高めることができます。
自分の心の中で考えて、気づきや理解することも大切ですが、話して外に出すことで、客観的に観ることができ、より多くのことに気づけたり、理解が深まることが多いものです。
実際どのような人がカウンセリングを利用しているのか?という疑問や質問に明確に答えられているわけではありませんが、時代の変化とともに利用者や利用する目的が広がってきています。
自分で乗り越えなきゃいけないんじゃないか?
「カウンセリング=話を聞いてもらうところ」というイメージが「カウンセリング=自分で乗り越えられない人が行くところ」というイメージにつながっていることも多くあるかもしれません。
自分だけでは乗り越えられないような問題や悩みがあることは悪いものでしょうか?
誰でもそのようなことが人生に一度や二度はあるかもしれません。
そういったところを協力して乗り越えることが悪いものでしょうか?
人間ならではの素晴らしい共生なのではないでしょうか。
上述しましたが、カウンセリングでは「話を聞いてもらう」受動性と「自らが気づき理解し、実行する」主体性の両面を持ち合わせています。
「カウンセリング=自分の力ではなくなる」ということではないということです。
積極的に主体性を持って行うカウンセリングは逆に「自分で乗り越える」ということを後押ししています。
このような誤解が多々あります。
また日本の伝統的な「自立心」を育てる教育によって「自分で乗り越えなければいけない」という気持ちが強くなっています。
それは素晴らしいものですが、かえって相談しにくくなる、相談できなくなることにつながってしまうこともあります。
いつも自分だけのチカラでなんとかしようとしてきた方にとっては「相談する」「他人の力を借りる」ことが自らの成長に役立ちます。
日本人は「恥じらい」に関して敏感な性質があると言われています。
それは大切な美徳でもありますが、「見栄」や「虚勢」を張ってしまうことにもつながります。
表面では苦しみを出さないようにして、一人心の中で苦しんでもがいているということが実に多くあります。
それを自分の力だけで乗り越えるのも大切ですが、人の力を借りることができる能力を備えていくことも同じくらい大切な時代になってきているように感じます。
カウンセリングに依存しないか心配
カウンセリングを受けると依存してしまうのではないかと心配になって足踏みしてしまうこともあります。
確かに依存してしまうこともあるかもしれません。
軽いものであれば問題ない場合もありますが、強い依存心の場合はクライエント自身にとって苦痛や不利益につながってしまうこともあります。
しかし専門的な知識を持っているカウンセラーは「その依存心」もテーマの中で扱いカウンセリングを行っていきます。
そしてそのような依存心も落ち着き、相談内容も軽減、改善、解決にいたり、カウンセリングは終了していきます。
ようするに「過剰な依存心」は重要なテーマであったりするのです。
ただ知っておいて欲しいことがあります。
美味しいレストランがあって、頻繁に通っている状態もある意味「依存」と言えます。
友達とまた遊びたい状態もある意味「依存」と言えます。
自分が愛してやまない好きなことやものもある意味「依存」と言えます。
このようにとてもいいことでも「依存」はあります。
私たちは協力して集団や社会を形成し、協力と依存をし合って生きています。
「依存」という言葉が非常に悪いイメージになっていますが、このように身近なもので、活用次第では良いものにも悪いものにもなります。
確かにカウンセリングは心理を扱う面でほかとは異なる趣があります。
カウンセラーとクライエント(相談者)との関係で「支配-服従」関係が成立してしまったり、宗教的になってしまうこともあるようです。
自分の力を使えなくなるような、先生に相談しなければ何もできなくなるような「依存関係」には最大の注意が払われねばなりません。
その部分に心配が起きることはとても良いことです。
信頼できるカウンセラーはその点に注意を払いながら、その気持ちを大切にしながら「依存心」に向き合うセッションを行っていきます。
そのような「依存心」には理由があって強くなったりするものです。
自分が相談したい相談所の「問い合わせ」でカウンセラーにそのような点を聞いて、どのような反応が返ってくるかがひとつの指標になるかもしれません。
ホームページなどで倫理規定を設けているところを探されるといいでしょう。
今自分にカウンセリングが必要か?
「自分にカウンセリングが必要かどうかわからない」という悩みがでることがあります。
それはどこか必要としているけど、本当に必要なのか?自分自身で乗り越えなきゃいけないんじゃないか?依存してしまうんじゃないか?本当によくなるのか?などの疑問や疑念で足止めされている状態かもしれません。
人は性格的特徴も遺伝子、問題、悩み、現在までの経験、考え方、捉え方など千差万別です。
ですので「このような状態でカウンセリングを受けたほうが良い」という基準を明確に提示できないのが現状です。
しかしこのページにたどり着いたということは、なにかしら必要性を感じていると言えます。
ですが、やめておいたほうが良いと思う理由付けもあると思います。
そのような方が多いため、この記事を書いているということもあります。
今自分にカウンセリングが必要か?という質問に対してお答えできるものとして「自分にとって有益かどうか?」という指標が大切なのではないかと思います。
自分にとって有益であれば、より良い結果が期待できます。
有益かどうか判断するために実際に「問合わせてみる」のもひとつの手です。
自分の状態でカウンセリングを受けることでどのようなことができるか?を聞いてみるのです。
しかしそれにも勇気がいります。
初めての経験であったり、自分の秘密にしていたことや大切なところを相談するので緊張することもあります。
相談するかどうか迷い、数週間や数ヶ月、長い人では数年という方もいらっしゃいました。
「もっと早く相談しておけばよかった」というお声を聞くことも多く、相談するまでに悩み、どのようなものかわからずいろいろな想像を膨らませてしまうことがよくあるようです。
このようなケースをなくすために、またミスマッチの回避と適切な相談先かどうかを判断できるため、当カウンセリングでは一度限りではありますが、10分無料電話相談を行っています。
おわりに
私はカウンセリングを行うカウンセラーであるため、カウンセリングに肯定的なイメージを持っていますのでそのような傾向の強い記事を記述をしていると正直思います。
現在まで約1万件以上カウンセリングを行っており、その魅力と注意しなければいけない点をよく知っています。
用いる技法やカウンセリングの流れ、性格、どこまで学習と研鑽をしているか、どのような倫理規定を持っているか、エビデンス(科学的根拠)を大切にしているか、クライエントの同意をしっかり得るかなどカウンセラーによって異なります。
ですので相談先は慎重に選ぶ必要が特にある世界です。
そのため、興味があるカウンセラーに問合せをし、ある程度の納得感をもってスタートを切れますように切に願っております。
また身体症状がある方や日常生活に支障をきたす心理的症状がある方は、まずは病院やクリニックで相談された上で必要に応じてカウンセリングを併用されることを推奨しております。

記事監修
公認心理師 白石
「皆様のお役に立つ情報を提供していきたいと思っています」